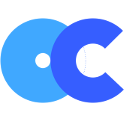お湯を沸かす、食品を冷蔵庫で冷やす、エアコンで部屋の温度を変えるなど、私たちは日常生活で「熱」を活用しています。また、人間の体が体温を一定に保とうとするように、私たち自身も熱をうまく使って生きている存在と言えるでしょう。
このように熱というものは、あまりに身近すぎるため普段は意識しないかもしれませんね。でもよく考えてみると、そもそも熱とは何でしょうか?
はるか昔から、人類は熱という概念を認識していました。しかし、その正体を明らかにし、活用できるようになるまでには長い年月がかかりました。まさに熱力学は、人類が苦労と試行錯誤の末に辿り着いた叡智の結晶のような理論なのです。
このコースでは、数学を使った熱の取り扱い方を学び、そして「エントロピー」という物理量を導入します。温度や圧力、体積などに比べて、エントロピーはあまり馴染みが無いかもしれませんが、統計力学や情報理論など他の分野にも繋がる非常に重要な物理量です。そして有名な「エントロピー増大の法則」(熱力学第2法則)について学びます。
また、このコースの最後には、応用例としてサーモグラフィーの原理やブラックホールと熱力学の関係性について学びます。熱力学が使える範囲は、実はとてつもなく広いということが実感できるはずです。きっと「熱力学はこんなことにも使えるのか!」と驚くことでしょう。
このコースは熱力学という物理学の理論について学ぶコースです。熱力学とはどんな理論なのか、全体像を見てみましょう。
西洋・東洋問わず、人類は古代から「物質とは何か?」を探求してきました。まだ熱力学が確立していなかった時代、人々は熱をどのように考えていたのかを学びます。
測定技術の発達した現代では「物質とは何か?」について多くのことが分かっています。現代的な視点での物質観と、熱力学がどの範囲をカバーする理論なのかを学びます。
熱力学が関係するのは、熱に関係する現象だけではありません。一見すると熱とは関係なさそうな物とも実は繋がりがあります。
このコースの目標と概要を確認します。
本コースのスライドをPDF形式でダウンロードできます。学習の補助資料としてご利用ください。
このセクションで学べることを確認しましょう。
普段使っている温度の単位(℃)以外にも、温度にはいろいろな定義の仕方があります。
華氏という温度の定義を学びます。
摂氏という温度の定義を学びます。
そもそも「熱の正体とは何か?」という謎に迫ります。
熱素説とは違う、「熱の正体」に対するもうひとつの考え方です。
物理学の全ての分野で需要な役割をする「エネルギー」の考え方を確認しておきましょう。
膨大な数の原子や分子を「何個」と数えるのは大変です。ではどうすればよいでしょうか?
熱力学を理解する上で欠かせない基本用語を確認しましょう。
熱力学では、普段私たちが日常生活で使っている温度の単位はあまり使われません。では、どのような定義の温度が使われるのでしょうか?
このセクションで学んだ内容のまとめです。
注目している系にはどんな種類のエネルギーが含まれているかを学びます。
ニュートン力学にも出てくる運動エネルギーの考え方について確認します。
ニュートン力学にも出てくる重力の位置エネルギーについて確認します。
ニュートン力学にも出てくるばねの位置エネルギーについて確認します。
なぜニュートン力学だけでなく、熱力学が必要になるのかということを理解します。
ミクロな視点から内部エネルギーの考え方を学びます。
物体の間に働く摩擦はとても身近な現象です。そのとき発生する熱の正体とは何でしょうか?
熱力学という理論の根幹となる、重要な法則を見ていきましょう。
参考書によっては、別の書き方をしている場合があるので混乱しないようにしましょう。
無限小、つまり微分の形で表現しておくと、後々役に立ちます。
エネルギーと熱・仕事には、本質的な違いがあります。やや抽象的に感じるかもしれないので「登山」の例えで説明します。
私たちが普段慣れ親しんでいる「お金」で例えると、熱力学第1法則の本質が見えてきます。
熱平衡という考え方は、熱力学では非常に重要です。系の物理量をどう定義するかに深く関わっています。
系が熱平衡でないときは、どんな状態になっているでしょうか?
系の状態を変化させる「過程」の分類を見ていきましょう。
ニュートン力学で最初に理想化された物体として「質点」を考えたように、熱力学の本質を捉えるための理想化された物質が「理想気体」です。
1+1=2という当たり前に見える計算は、すべての物理量で本当に成り立つのでしょうか?当たり前だと思っていることが意外と盲点になっているかもしれません。
温度や圧力・体積といった物理量は馴染み深いですが、熱力学では、ここにもうひとつ仲間が加わります。
系に出入りする仕事を、具体的な物理量を使って書き換えてみましょう。
内部エネルギーと温度を結び付ける物理量の定義を見てみましょう。
熱容量は具体的には何を意味しているのかを学びます。
定積熱量量と定圧熱容量の間には、ある関係式が成り立ちます。その関係式の簡単に導く方法を学びます。
気体を原子や分子の集合体と考えて、ニュートン力学と統計的な手法を使って熱力学的な性質を導きます。(前編)
気体を原子や分子の集合体と考えて、ニュートン力学と統計的な手法を使って熱力学的な性質を導きます。(後編)
温度というマクロな物理量と分子の運動というミクロな現象を結びつける非常に重要な法則です。統計力学とも深い関わりがあります。
熱を仕事に変えることができる仕組みを学びます。熱力学を理解する上で、とても重要な概念です。
熱機関が抽象的でわかりづらい場合は、もう少し具体的な力学的に動く機関をイメージしてみましょう。ここでは水車を例に考えてみます。
熱機関には、自発的に起きる動作とそうでない動作があります。その違いは何でしょうか?
熱機関の繰り返し動作を考える場合、数学の「閉ループ」という図形との対応が見えてきます。
熱サイクルを動かすための準備です。まずは体積と圧力をそれぞれ一定にした場合の過程を見てみましょう。
系が外界にする仕事は、ある図形の面積と考えることができます。
系と外界の間で熱のやり取りが無い場合の過程を考えてみましょう。
いろいろな熱サイクルの中でも代表的なものがカルノーサイクルです。この後出てくるエントロピーの定義に繋がる重要な考え方です。
熱機関の効率に関する重要な法則を学びます。(前編)
熱機関の効率に関する重要な法則を学びます。(中編)
熱機関の効率に関する重要な法則を学びます。(後編)
熱と温度の組み合わせには、ある不等式が成り立つことを学びます。
カルノーサイクルでない任意のサイクルを扱えなければ、熱力学は非常に不便な理論になってしまいます。何とか、これまでの知識を使って扱えるようにできないか考えてみます。
いよいよ「エントロピー」の数学的な定義を行っていきます。
エントロピーを使って熱力学第2法則を数学的に表してみましょう。
温度とエントロピーを軸に取ったグラフを使うと、熱を図形的に表現することができて便利です。
断熱過程でのエントロピーの性質から、以前出てきたポアソンの法則を導いてみましょう。
エントロピーは定義を見ても、なんだか抽象的で分かりづらいかもしれません。具体例で計算しながら、使い方に慣れていきましょう。
以前出てきた内部エネルギーとエンタルピーについて、もう一度考察してみましょう。
内部エネルギーとエンタルピーは、数学的にはルジャンドル変換という計算に対応していることを学びます。
ルジャンドル変換によって、エントロピーではなく、温度を変数に取るエネルギーを2種類作ることができます。こちらの方が人間にとって制御しやすくて便利です。
新たに定義した2つのエネルギーは、具体的に何を表し、どんなことに使われているのでしょうか?
熱力学第1法則は、数学的には、ニュートン力学に出てきた保存力とよく似た形をしています。それを利用して、数式のイメージを掴んでいきましょう。
ポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)から保存力を導けたように、熱力学ポテンシャルからは熱力学的な変数を導くことができます。力学との数学的な類似性をうまく活用しましょう。
熱力学に出てくる変数の間には、ある関係式が成り立つことを学びます。
熱力学を使いこなすには、必要な時に、必要な数式を「思い出せる」ことが重要です。丸暗記は挫折しがちなのでおすすめできません。それよりも、効率よく思い出す方法を学びましょう。
ルジャンドル変換の思い出し方です。
物理量を熱力学ポテンシャルから導く方法の思い出し方です。
マクスウェルの関係式の思い出し方です。
触らずに温度を測れる装置、あるいは温度の分布を画像として表示する装置は、いったいどんな原理動いているのでしょうか?
熱平衡状態の電磁波を考えると、温度と放射エネルギーの関係が見えてきます。
熱力学第1法則から導かれる、非常に重要な方程式です。
熱平衡状態の電磁場を光子(フォトン)というエネルギーの粒の集合体を考えると、理想気体の考え方を応用することができます。アインシュタインの関係式というものを利用した、実に巧妙な考え方です。
前に導いておいたエネルギー方程式を使って、シュテファン・ボルツマンの法則を導いてみましょう。
ブラックホールと熱力学は、一見すると何の関係も無さそうに見えます。どちらも物理学の範疇ではありますが。しかし最先端の宇宙論では、それらがうまく融合しています。
中学や高校で習う公式や、このコースに出てきた考え方を使って、ブラックホールの「温度」を計算してみましょう。「熱力学はこんなことにも使えるのか!」と驚くことでしょう。
このセクションで学んだ内容と、このコース全体のまとめです。
OpenCourser helps millions of learners each year. People visit us to learn workspace skills, ace their exams, and nurture their curiosity.
Our extensive catalog contains over 50,000 courses and twice as many books. Browse by search, by topic, or even by career interests. We'll match you to the right resources quickly.
Find this site helpful? Tell a friend about us.
We're supported by our community of learners. When you purchase or subscribe to courses and programs or purchase books, we may earn a commission from our partners.
Your purchases help us maintain our catalog and keep our servers humming without ads.
Thank you for supporting OpenCourser.