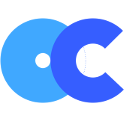1.【受講者の悩みや問題】
ミッション・ビジョン・バリューやパーパスについて会社から与えられてはいるが、どのように活用し、自分に落とし込めばよいか分からない
逆に、ミッション・ビジョン・バリューを広めていく立場として、どのように浸透させればよいか分からない
ミッション・ビジョン・バリューも所詮はきれいごとであり実際のビジネスに影響するものではないと思っている
会社のミッション・ビジョン・バリューと自分の思いや価値観をどのようにすり合わせればよいかが分からない
自分の夢や価値観と会社は切り離して考えるしかないと思っている
そんなあなたのために、このコースを作りました!
2.【このコースの特徴】
1.【受講者の悩みや問題】
ミッション・ビジョン・バリューやパーパスについて会社から与えられてはいるが、どのように活用し、自分に落とし込めばよいか分からない
逆に、ミッション・ビジョン・バリューを広めていく立場として、どのように浸透させればよいか分からない
ミッション・ビジョン・バリューも所詮はきれいごとであり実際のビジネスに影響するものではないと思っている
会社のミッション・ビジョン・バリューと自分の思いや価値観をどのようにすり合わせればよいかが分からない
自分の夢や価値観と会社は切り離して考えるしかないと思っている
そんなあなたのために、このコースを作りました!
2.【このコースの特徴】
たった3時間の動画コースでミッション・ビジョン・バリューやパーパスの歴史的背景や具体事例、その実践方法について理解することができる。また、日本においてなぜ浸透が難しいかの説明も行っている。
単なるフレームワークとしてのミッション・ビジョン・バリューではなく、1つでよいので徹底的に使うことが成功の秘訣であるという点を指摘している
各層のリーダーが、自分事としてビジョン構築し、リーダーシップを発揮するためのポイントを理解できる
リーダー層がいかにミッション・ビジョン・バリューを使うかだけではなく、その受け手である社員・メンバーの立場から、ミッション・ビジョン・バリューにどのように向き合えばよいかについて理解できる
たくさんの有名企業の事例を紹介しており、実際にミッション・ビジョン・バリューに生きるというのはどういうことなのかを体感的に分かるように設計されている
ミッション・ビジョン・バリューやパーパスを「持つべきもの」と前提するのではなく、理解したうえで各社がその採用を検討すべきという立場から作成されている
3.【カリキュラムの概要】
第0章:はじめに
第1章:ミッション・ビジョン・バリューとは
第2章:ミッション・ビジョン・バリューの策定と浸透
第3章:リーダーの役割 ~外部環境を踏まえたビジョン構築
第4章:メンバーのミッション・ビジョン・バリューへの向き合い方
■ 補足事項
基本的に事例は2024年度(コース作成時の最新情報)までのものを使っています
コースの目的と全体像を確認します。また、コース成功の条件について、以下の点をお伝えします。
・楽しく取り組むこと
・本当の意味で「徹底すること」の意味をよく考えること
・与えられたミッション・ビジョン・バリューではなく、自分はどうしたいのか、「自分」と向き合うこと
まず簡単にミッション・ビジョン・バリュー(MVV)とは何かを押さえ、そもそもそういうものは必要なのかどうかを考えましょう。ミッションがあるとやりがいが上がるというのは本当でしょうか?是非ご自身に置き換えて考えてみてください。
次に歴史的にMVVへの着目がどのようになされてきたのかを確認しましょう。もともとの由来を知ることもMVVの深い理解に結び付きます。MVVという3点セットと言われますが、必ずしも3つある必要がないというのも分かるはずです。
エンゲージメントを高めることで劇的に生産性が上がるのが人的資本の特徴ですが、ではどうしたらやる気(エンゲージメント)は上がるのでしょうか。ここでは人間の認知のあり方も含めて解説します。
近年、モノの充足が進んでくるとイミ消費などの購買形態が増えてきています。若者中心に「なぜ働くのか」「なぜその商品を買うのか」といったそもそもの理由が求められるようになっています。その意味で、企業にとっても改めてなぜ自社はその製品・サービスを扱っているのかの理由を深掘りすることは重要になっているといってよいでしょう。
ここでMVVが浸透している企業として有名な事例を見てみましょう。ミッション、ビジョン、バリューのそれぞれがうまく機能して成功している会社としてソニー、フィリップ・モリス、ジョンソン&ジョンソンを取り上げます。
近年のパーパスについてもここで触れておきましょう。基本的にはMVVと同じ文脈ですが、より主体的に社会的な役割を位置づけていくことにパーパス経営のポイントがあります。今までの大きな流れとMVVとの違いを押さえておきましょう。
ミッション・ビジョン・バリューのような社会的な役割や目標、あり方を示すものはどの企業にも昔からあるもので、あえてMVVのフレームワークに当てはめる必要性は本来ありません。ここでは本コースにおけるMVVの用語の整理をしておきます。
1章の最後に、日本におけるMVV浸透の難しさについて考えます。西洋のようにキリスト教やイスラム教といった一神教で聖典がある世界と日本では社会的な発想が根本的に異なります。また、他民族が共存して意思疎通を図る必要がある世界と、基本的に島国で同質性が高い社会である日本では、やはりコミュニケーションの前提が大きく異なります。このあたりを意識したうえで社内におけるMVVの活用を考えていけるとよいでしょう。
MVVを策定するにあたって、それぞれの役割の違いを考えましょう。ここでは佐宗邦威氏の説明を借り(ボイドモデル)群れを維持するためのしくみとしてのMVVを考えます。
次に、企業のライフサイクルに応じて求められるものが異なるという点を説明します。常に企業がMVVの3点セットを持つ必要はなく、その時々に必要なものを1つでも徹底すれば成果は上がるということを理解しましょう。
まずビジョンについて扱います。ビジョンの条件は何か、どのような事例があるか、策定のためにどのようなワークが有効かを説明します。
■扱う事例
・キング牧師/ソフトバンク/トニーズチョコロロンリー
次にバリューについて具体的に見ていきましょう。企業における価値観、あるいは行動規範と呼ばれるバリューですが、とにかくワーディングにこだわることが重要です。そして一度決めたら必ず守ること、徹底的に守ること、それが尖った企業文化を作っていきます。
■扱う事例
・Apple/アサヒビール/ソニー/サイバーエージェント/ハーレーダビッドソン
最後にミッションの策定について考えます。ミッションは設立当初からあるというよりも、事業が多角化していく中で再度自社を見直すタイミングに威力を発揮します。講義の中ではアイデンティティのアップデートという言い方をしていますが、是非その感触をつかんでください。
■扱う事例
・新渡戸稲造/レゴ
ミッションについての補足です。これまでの通り、ミッションは企業における壮年期に自社のアップデート、断捨離として必要となるものと考えれば、創業時に無理やり作る必要性はありません。無理に社会全を語ろうとすると身の丈に合っていない言葉が並ぶもの。しっかり今何をすべきかを考えて設定しましょう。
ここではMVVの浸透について、浸透のさせ方というよりもむしろどこまで徹底するのかという観点で説明します。重要なことは徹底することで、一つでも徹底していけばそれが浸透していくはずなのです。逆に言えばローカルルールを設けたり、是々非々で判断していてはいつまでたっても浸透することはないでしょう。その執着心ともいうべき徹底に関して考えましょう。
■扱う事例
・マッキンゼー/ジョンソンエンドジョンソン
MVVの浸透の為によく使われる手法として会社の歴史を語ること、また社員個人の経営理念に沿ったストーリーについて説明します。これは意識的・無意識的問わずに各社で取り入れられている手法でもありますが、改めて自社のあり方を見つめ直すためにも重要な観点です。
この章では大小問わずそれぞれのチームリーダーに求められるビジョン構築について扱います。ビジョンの構築において最も重要なことは外部環境への変化を洞察し、そこにビジネスチャンスや脅威を見出すことです。この変化が構造的で大きければ大きいほど自社や自チームに与える影響は大きく、本質的な問題となるでしょう。ここでは明治維新時の西郷隆盛の事例を紹介しながらその影響の大きさを実感します。
■扱う事例
西郷隆盛と明治維新
次に変化への洞察事例として近年の「第4の波」という変化、またここ20年ほどのソフトウェアの重要性の変化について触れておきたいと思います。一つの事例ですが、皆さんの業界においても構造的変化が起きていないかどうか、是非考えてみてください。
ビジョン構築がリーダーに必要であるのは、それがメンバーとの信頼関係に直結するからです。チームをまとめていくためにはリーダーシップが必要ですが、まずメンバーとのラポールはどのような理屈で形成されるかを理解しましょう。
ラポールの仕組みを学んだうえで、ビジョン構築がなぜラポールを生むのか考えます。場の定義づけ、場の支配というのは人の認知に大きな影響を与えるものです。より視座の高いビジョンを構築することで大きな影響力を発揮できるようになるでしょう。
それでは外部環境の変化をどう洞察したらよいのでしょうか。それは丁寧な現状把握をするしかありませんが、その際のポイントを指摘しておきます。事実の羅列ではなく、それをどう「評価」するかにこだわりましょう。
ビジョン構築で実際上難しいところは、どのような言葉を選ぶかということです。徹底するにしても、それがメンバーの創造性を奪うものであっては今の時代のビジョンとしては不適切でしょう。一方で方向性は明確に理解されないといけません。試行錯誤ではありますが、発展的な課題としてぜひ検討してみてください。
最後の第4章ではメンバーがMVVとどう向き合うかについて考えます。社員の立場としてはここが最も重要かもしれませんが、要するにMVVは与えられるものではないということです。社会の方向性はリーダーが示すものですが、それに盲目的に従ってしまうと大きな失敗を生むのは歴史が証明しています。私たちは自分自身のMVVがあったうえで、会社や組織と付き合っていく必要があるのです。
目標管理の断面でGoogleなどが採用しているOKRについても触れておきましょう。これは元インテルCEOのアンドリュー・グローブが提唱している目標管理の手法ですが、これもまた主体的で野心的な目標設定を前提としています。アンドリュー自身がコロンブスの事例を挙げていますので、参考にしていきましょう。
個人のMVと組織のMVは違ってもよく、違って当然でもあります。一方で組織に属している以上、あまりに異なる方向性ではお互いに不幸になるのは目に見えていますし、その組織に属そうと思ったということは方向性に共感できるからでもあるでしょう。個人のMVと組織のMVとの関係を考えていきます。
個人のMVと組織のMVの関係は大きく3つに分けられます。組織のビジョンなんて自分には関係ないと思っている方でも、あたらめて自分の夢やビジョンとの関係性を考えてみると新しい見え方ができるかもしれません。特に抽象度を上げて共通の目標を設定する方法は重要ですので、ぜひ理解をしておきましょう。
多くの問題というものは対立している同じ次元では解決できないものです。解決するには一段抽象度を上げる必要があるということについて補足します。
自分のMVVと言われてもピンとこない、日々の生活で精いっぱいであったり、あるいは既に満足しているという方もいると思います。それでもなお、自分のMVVを持とうというのはどういうことでしょうか。改めて是非考えてみてほしいテーマです。
会社のバリューを考えるにあたっては、まず自分自身のバリューと向き合う必要があります。ご自身の価値観を改めて振り返り、時間をかけて言語化してみましょう。
バリューについて、価値観を自分の言葉に直すことはいきなりは難しいものです。よくあるミスを説明しますので、ご自身の言い換えについてブラッシュアップするきっかけとしてください。
次に、明らかになった今の自分の価値観をベースに、会社のバリューを自分なりに言い換えるというワークを行います。こうすることでより自分自身に引き寄せた、自身のある行動規範(バリュー)となっていくでしょう。妥協せず、自分が納得できるまでワーディングを練り上げましょう。
全体のまとめをします。MVVについて改めて学ぶと、会社と自分を振り返る良い機会になるでしょう。流行に乗ってMVVやパーパスと言うのではなく、折角使うのであれば意味のある使い方をし、自社に適切な形で運用してほしいと思います。MVVは日本で浸透させる難しさがあり、また徹底するからこそ意味を持つものでもあります。そしてそれは私たち自身の人生そのものへの向き合い方でもあるでしょう。是非このコースがご自身と向き合う一つのきっかけにもなれば嬉しく思います。
OpenCourser helps millions of learners each year. People visit us to learn workspace skills, ace their exams, and nurture their curiosity.
Our extensive catalog contains over 50,000 courses and twice as many books. Browse by search, by topic, or even by career interests. We'll match you to the right resources quickly.
Find this site helpful? Tell a friend about us.
We're supported by our community of learners. When you purchase or subscribe to courses and programs or purchase books, we may earn a commission from our partners.
Your purchases help us maintain our catalog and keep our servers humming without ads.
Thank you for supporting OpenCourser.